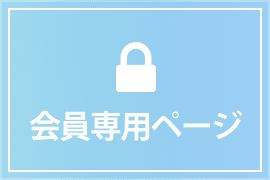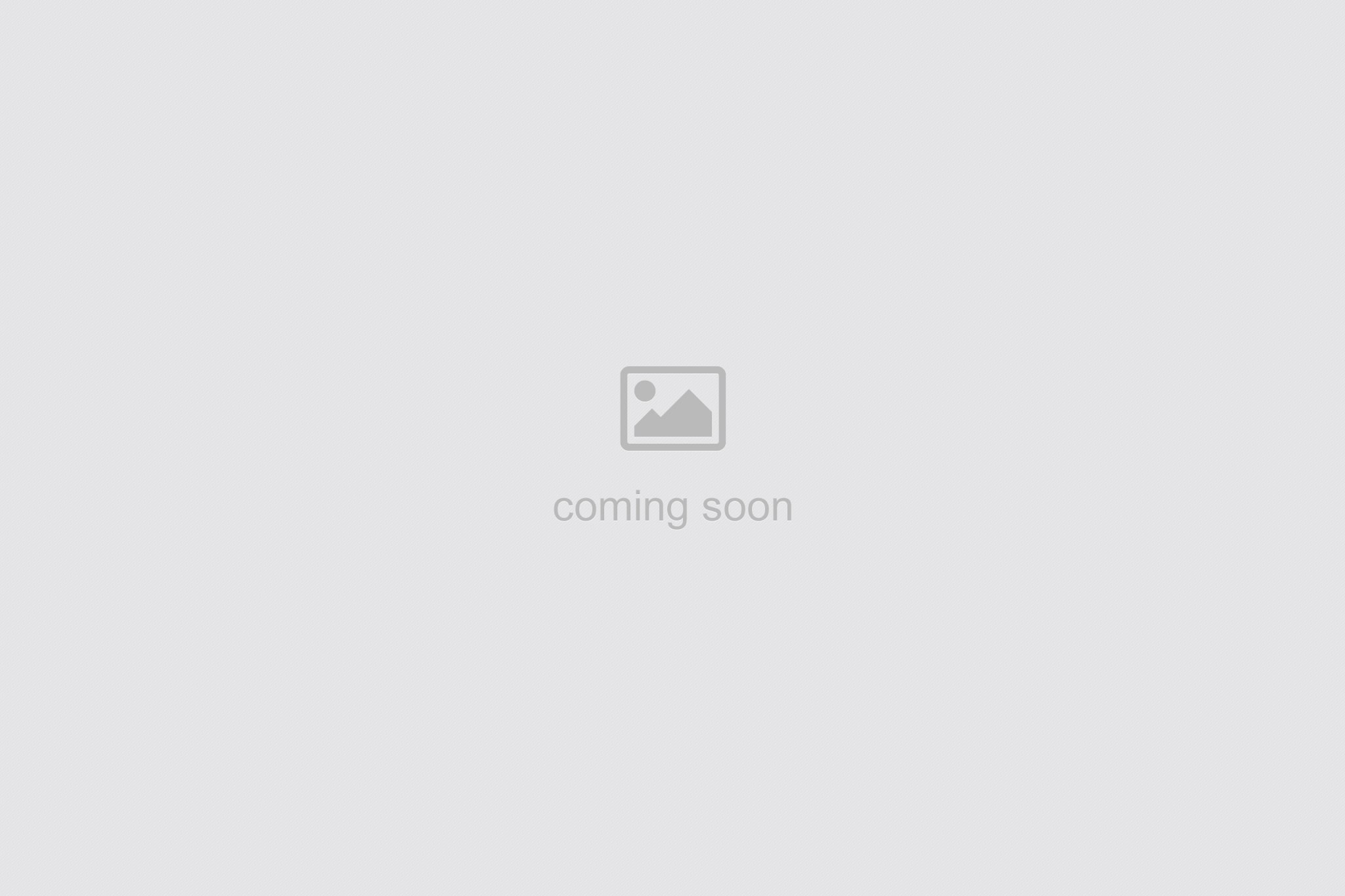中越地震被災地仮設貯水槽の維持管理事業(H17~18年の2年間)
中越沖地震被災地仮設貯水槽の維持管理事業(H19~20年の2年間)
設置者、管理者から相談と指導
H10.8 集中豪雨災害時の新潟市内冠水貯水槽の調査と消毒
H 8.2 長岡市中心部大口径水道管破裂時の冠水貯水槽の調査と消毒

| 回 数 | 事業年度 | 研修年月 | 協会員数 | 非会員数 | 合計 | 登録事 業所数 | 備 考 |
| 昭和52年度 | 52年 7月 | 80 | ― | 80 | 協会員のみ対象 | ||
| 昭和53年度 | ― | 0 | 協会員のみ対象 | ||||
| 昭和54年度 | 261 | ― | 261 | 協会員のみ対象 | |||
| 昭和55年度 | 59年11月 | 121 | ― | 121 | 協会員のみ対象 | ||
| 1回 | 昭和56年度 | 56年 9月 | 318 | ― | 318 | 105 | 知事登録制に改正・協会員のみ対象 |
| 2回 | 昭和57年度 | 57年12月 | 312 | ― | 312 | 112 | 協会員のみ対象 |
| 3回 | 昭和58年度 | 58年12月 | 344 | ― | 344 | 114 | 協会員のみ対象 |
| 4回 | 昭和59年度 | 59年11月 | 337 | ― | 337 | 113 | 協会員のみ対象 |
| 1回 | 昭和60年度 | 61年 2月 | 384 | 18 | 402 | 118 | 指定団体による制度改正・全事業者を対象とする |
| 2回 | 昭和61年度 | 62年 2月 | 404 | 14 | 418 | 126 | 全事業者を対象 |
| 3回 | 昭和62年度 | 63年 3月 | 411 | 26 | 437 | 130 | 全事業者を対象 |
| 4回 | 昭和63年度 | 元年 3月 | 434 | 31 | 465 | 133 | 全事業者を対象 |
| 5回 | 平成元年度 | 2年 3月 | 441 | 37 | 478 | 136 | 全事業者を対象 |
| 6回 | 平成2年度 | 3年 3月 | 453 | 29 | 482 | 131 | 全事業者を対象 |
| 7回 | 平成3年度 | 4年 3月 | 438 | 29 | 467 | 132 | 全事業者を対象 |
| 8回 | 平成4年度 | 5年 2月 | 438 | 26 | 464 | 132 | 全事業者を対象 |
| 9回 | 平成5年度 | 6年 2月 | 469 | 30 | 499 | 135 | 全事業者を対象 |
| 10回 | 平成6年度 | 7年 2月 | 448 | 38 | 486 | 143 | 全事業者を対象 |
| 11回 | 平成7年度 | 8年 2月 | 491 | 29 | 520 | 143 | 全事業者を対象 |
| 12回 | 平成8年度 | 9年 2月 | 460 | 43 | 503 | 148 | 全事業者を対象 |
| 13回 | 平成9年度 | 10年 2月 | 473 | 55 | 528 | 153 | 全事業者を対象 |
| 14回 | 平成10年度 | 11年 2月 | 470 | 40 | 510 | 153 | 全事業者を対象 |
| 15回 | 平成11年度 | 12年 2月 | 474 | 53 | 527 | 153 | 全事業者を対象 |
| 16回 | 平成12年度 | 13年 2月 | 467 | 65 | 532 | 156 | 全事業者を対象 |
| 17回 | 平成13年度 | 14年 2月 | 476 | 62 | 538 | 158 | 全事業者を対象 |
| 18回 | 平成14年度 | 15年 3月 | 480 | 70 | 550 | 160 | 全事業者を対象 |
| 19回 | 平成15年度 | 16年 2月 | 495 | 67 | 562 | 159 | 全事業者を対象 |
| 20回 | 平成16年度 | 17年 2月 | 489 | 74 | 563 | 163 | 大臣登録制による制度改正・全事業者を対象 |
| 21回 | 平成17年度 | 17年12月 | 443 | 46 | 489 | 166 | 全事業者を対象 |
| 22回 | 平成18年度 | 18年11月 | 402 | 35 | 437 | 165 | 全事業者を対象 |
| 23回 | 平成19年度 | 20年 2月 | 395 | 28 | 423 | 166 | 全事業者を対象 |
| 24回 | 平成20年度 | 21年 2月 | 391 | 42 | 433 | 167 | 全事業者を対象 |
| 25回 | 平成21年度 | 22年 2月 | 391 | 30 | 433 | 170 | 全事業者を対象 |
| 26回 | 平成22年度 | 23年 2月 | 390 | 31 | 421 | 163 | 全事業者を対象 |
協会一括受託による会員一斉清掃体制の新潟市営住宅での一例を紹介
新潟支部全会員51社にて、約70棟の貯水槽清掃を平均1住宅団地単位で実施、貯水協の代理者として会員に担当割り当てを行う。
開始1週間前に全会員を召集、詳細を徹底する。
担当現場の指定・作業内容の確認・遵守事項の説明。
事前点検実施方法・工程表・作業員資格者名簿・検便検査名簿・誓約書の提出、清掃開始までに、協会は実務経験と管理監督判断能力のある人材を、会員内部より指導監督者として約20名を選抜する。
清掃当日は、指定住宅団地の担当住宅現場に担当会員(10乃至15社)が待機し、午前9時(終了又は断水は午後4時までに制限してある)を目途に一斉に作業を開始する。
開始と同時に、協会指導監督者は、1人が2~3社を監督対象として受け持ち、工程の確認→作業員名簿及び検便名簿の整合性の確認→ユニフォーム・資機材の清潔度の確認→開始時間・開始時残留塩素測定結果の確認を実施する。
清掃後の、100㎎/㍑及び500㎎/㍑の消毒に対して、消毒液濃度を測定し、消毒の確実性を確保している。
清掃時間中受け持ち現場の巡回、突発自体・緊急補修工事発生の対処等指示する。 清掃終了時、終了直後水質検査結果の確認。
各住戸の水栓開放異常を個別メーター点検により確認(異常発見住戸はメーター止水栓の閉止して張り紙貼付で注意連絡と住宅班長に連絡する)。
清掃終了確認は、前記作業と各水槽が満水自動停止確認をもって終了とする。
但し、各住戸への給水は、午後4時には必ず開始する、満水停止確認は夜間・深夜になるケースもある。
住宅班長に清掃後、緊急事態対処としての今後24時間の連絡、対応先を文書で連絡する。
指導監督者の確認を経て作業完了となる 。
その他同様事例は、新潟市・長岡市・上越市・県内大手事業所等で、約300件相当を会員の一斉清掃体制で協力させていただいている。